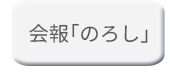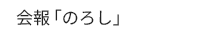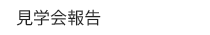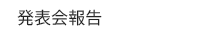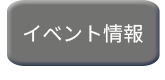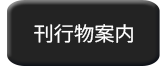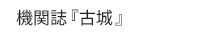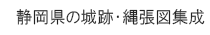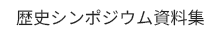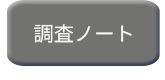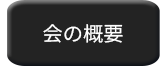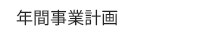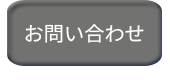�@����̌��w�n�͈��m���V��s�̍��~�n(�W����530m)�ł��B�{��ɂƂ��Ă͕��� 19 �N(2007 �N)�ȗ�18�N�Ԃ�̃t�B�[���h���[�N�ɂȂ�܂��B���̒n��ɂ͋����͈͂ɏ�s���W�����đ��݂��Ă��܂����A���T�N��(1570�`1572)����̓���vs.���c�̍U�h�ɋ����e�������v�Ւn�ł��������Ƃ��A�u�˂��������Ȃ���w�ׂ��s�t�@���K���̗��j�ό��G���A�ł��B�����̂��Q���������҂������܂��B
�� ���{�� �ߘa�V�N3��23���i���j
�� ���w�n �ǃm�_��E����R��E����E�T�R��E�Ë{��
�� �S���� �V�c�F�������A��؈�K����
�� �Q���� ���6,000�~�A����7,000�~
�� �o�X �s��̃o�X
�� �r�̓��x�� �����������i�R�j
�� �\���� �����炩��☞ s-kojouken@outlook.com
�� ���ؓ� �ߘa7�N3��19���i���j���A���A����ɂȂ莟����ߐ�܂�
�� ���28��
�� �g�x�x �n�C�L���O���x�̕����i����ɂ����C�E�J��j�E�ٓ��A������
�@�� ���V��̏ꍇ�́A�����ߑO�U���̎��_�Œ��~�܂��͉����f���Ă��m�点���܂�
�� �����i�\��j
�@8�F00 JR���w�k���W���A�o�X�o��
�@8�F10 ���������E��IC
�@8�F45 �@���}PA �i��Ԓn�j
�@9�F10 �@ �O����PA�i��Ԓn�j
�@9�F20 �@�O�P��JC �@���@�V�����������H��
10�F00 �V���������E�V��IC
10�F10 ���̉w�u��������V��v �g�C���x�e
��
11�F10 ���̉w�u���Ŏ��葺�v �i�o�X���ԏꏊ�j
11�F40�`12�F05 �ǃm�_�錩�w
12�F35�`13�F15 ����R�錩�w�i���H�j
13�F50�`14�F10 ���錩�w
���̉w�u���Ŏ��葺�v�i�o�X���ԏꏊ�j
14�F20�`14�F45 �T�R�錩�w
15�F00�`16�F00 �Ë{�錩�w
�@�@�@�@ ��
16�F40�`17�F00 ���̉w�u��������V��v
��
17�F10 �V�����������H �V��IC
17�F50 �O�P��JC �@���@�����������H��
18�F00 ���������E�O����PA �i���Ԓn�j
18�F25 ���������E���}PA �i���Ԓn�j
19�F00 JR���w��� ���U
�����u�̂낵�v��336��PDF

![�]���P](/images/menu_img/pc/6d1f83a373737bbc62d565cec77f088a.png)